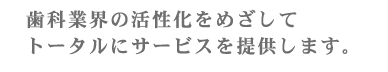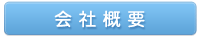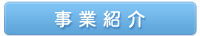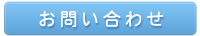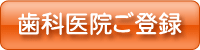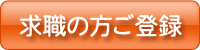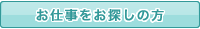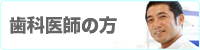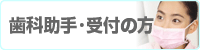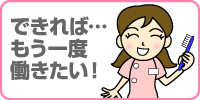歯科医院の先生方 ご存知ですか?
歯科医院の先生方、スタッフを雇用するにあたってどのような取り決めがあるか、ご存知でしょうか。
取り決めをはっきりしておくことは、お互いに心おきなく仕事をしていくための源になり、いざというときに前向きに解決できる基礎になります。
思わぬ気持ちのすれちがいが起きないように、この機会に確認されてはいかがでしょうか。
労働条件の通知義務について
従業員を雇用するとき、本人に労働条件を書面(労働条件通知書・雇用契約書等)で交付する義務があることをご存じでしょうか?
書面にすることで、あとあと労働条件を確認することができ(言った・言わないの水掛け論にならない)、労使間でトラブルが発生した際には、この書面をもとに問題を解決することができる、といった利点があります。就業規則を書面で交付することでもかまいませんが、従業員が10名未満の医院では、就業規則の作成義務はありません。採用時にはぜひ、労働条件についての書面を作成・交付されることをお勧めします。
<最低限必要な記載事項>
・契約期間 ・就業の場所 ・従事すべき業務の内容 ・始業、終業の時刻、休憩時間 ・時間外労働の有無 ・休日 ・休暇(年末年始休暇、夏期休暇、有給休暇等) ・賃金に関する事項(賃金額、計算方法、割増賃金の計算方法、締日、支払日、支払方法) ・退職に関する事項(定年制の有無、自己都合退職の告知時期、解雇等)
<任意事項:なければ書かなくてよい>
・賞与 ・退職金
労働時間について
所定労働時間と法定労働時間の違いをご存知でしょうか?
法定労働時間とは、国が定めている1日8時間、1週40時間(従業員10人未満の医院は44時間)のことで、所定労働時間とは、医院が従業員に対して労働条件として定める1日、または1週の労働時間のことをいいます。医院では1日8時間以上の労働時間となることが多いですのでご注意ください。
また時間外労働(残業)について、事業主には「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」というものを労働基準監督署に届け出る義務があります。本来であればこの届出をせずに、従業員に時間外労働又は休日労働をさせることは労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、という罰則があるのです。これは要注意事項です。
休憩時間について
1日8時間をこえる労働をさせる場合には1時間の休憩、6時間をこえ8時間以内であれば45分の休憩をもうけなくてはなりません。ただし、6時間以内であれば休憩時間はもうけなくてよいとされています。8時間をこえる場合何時間であっても、法律上休憩時間は1時間でよいことになっています。
有給休暇について
有給休暇は、雇用した日から6ヶ月経過後に、その間の出勤率が8割以上であれば、法律上当然に付与されるものです。医院に有給休暇に関する規定が存在しなくても、 従業員は医院に対して有給休暇を請求する権利があるといえます。有給休暇については、付与日数、請求時期や方法などルールをまえもって作っておくことをお勧めします。
<有給休暇の付与日数>
| 勤続年数 | 6ヵ月 | 1年 6ヵ月 |
2年 6ヵ月 |
3年 6ヵ月 |
4年 6ヵ月 |
5年 6ヵ月 |
6年 6ヵ月以上 |
| 有給休暇の 付与日数 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
賃金について
賃金の支払いについては、下記の5原則があります。
(1)通貨で(従業員の同意を得れば金融機関への振込可) (2)直接 (3)全額を (4)毎月1回以上 (5)一定期日 支払う
賃金額については産業別、又は地域別に最低賃金額というものが決められています。この金額(東京都では現在、時間給換算で766円)未満で働かせることは最低賃金法違反となり、院長は罰則の対象となってしまいますのでご注意ください。
また、賃金に関してもうひとつ気をつけなくてはならないのが、残業に対する割増賃金です。 1日8時間を超えて働かせた場合は2割5分増し、夜22時以降に働かせた場合も2割5分増し、休日に働かせた場合は3割5分増しの割増賃金を支払う義務が発生しますので、ご注意ください。
解雇について
一般的には、これといったの理由がないのに、従業員を解雇することはできないのが原則です。
ただ、何か問題のある場合に関しては、30日以上前に、「○月○日に貴方を解雇します」という解雇予告をすることで解雇することができます。即時解雇の場合には、解雇予告手当といって、30日分の給与を支払うことで即時解雇することができます。これは医院が設定した試用期間内であっても同様です。ただし、雇い入れ後14日以内に解雇するのであれば、この解雇予告および解雇予告手当の支払は必要ありません。
退職金について
「退職金を支払う義務ってあるの?」というご質問をよく聞きますが、取り決めをしていなければ、退職金を支払う義務はありません。
気を付けていただきたいケースとしては、「何となく院長の裁量で金額を決めて渡している」という場合です。このようなケースでは、「○○さんは、勤続10年で退職金を40万円もらったのに、△△さんは、勤続10年で20万円しかもらわなかった」というようなことがあると、従業員の不信感の原因となることがあります。
退職金に関するルールを先に決めておくことで、院長も従業員も気持ち良く退職を迎えることができます。
社会保険について
従業員が5人以上の医院では、健康保険と厚生年金保険に加入しなくてはなりません。医療法人の場合は、従業員数に関係なく加入しなければなりません。保険料は医院と従業員で折半負担となります。
健康保険については、都道府県ごとに歯科医師国民健康保険組合(例外:東京都)があり、歯科医師会に加入している場合にはこの保険に加入できます。この保険を適用できない場合は、従業員は各々市区町村国民健康保険に加入することとなります。
労働保険について
個人事業であるか、医療法人であるかにかかわらず、また従業員数に関係なく、1人でも従業員を雇った場合には、労災保険にはかならず加入しなければなりません。また週20時間以上労働する従業員がいる場合には、雇用保険にも必ず加入しなければなりません。
トラブルを避けるために
日頃、従業員と、あらたまって雇用や労働についての話し合いをする時間がとりにくい場合は、専門家に入っていただくことをお勧めします。
社会保険労務士の方に、月に一度でもスタッフに声をかけてもらう機会を作るなど、小さな疑問や不安をため込まずに解決する機会を設けるだけで、気持ちの良い職場環境を作ることができます。
【以上の内容について、法の改正等により、事実と異なる場合もあります。詳しくは専門家にご確認下さい。また、他コンテンツへの文章の引用・転載を禁じます。】