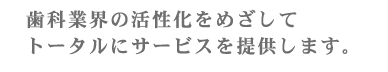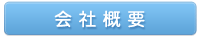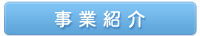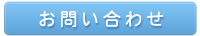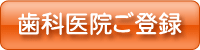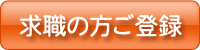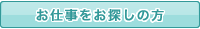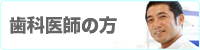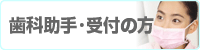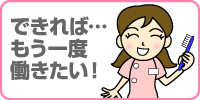働いていて困ったときには…
雇用されていて、困ったことがあり、どこにも相談できない状況になった時、あなたならどうしますか?
最近は、ネットの発達により、検索で調べたり、ソーシャル・ネットワーキング・サービスなどを利用して同業の方に相談したりと、いろいろな相談ができるようになりましたが、それで解決につながる場合もあれば、確かでない情報にふりまわされてしまい、解決につながらない場合もあるようです。どうすれば前向きに解決できるか、参考にしてください。
労働条件を知りましょう!
自分の働く労働条件(時間、休日・休暇、賃金、退職についてなど)をよく確認し、納得したうえで仕事を始めましょう。採用されるまでに、面接などで不明な点は必ずはっきりさせておくことです。
だれに相談する?
雇用されてから困ったことが発生し、直接院長に相談しにくい場合には、医院にかかりつけの社会保険労務士がいれば、その方に相談するのが一番です。
そうでない場合で、本当に困った時は、ハローワークや労働基準監督署に電話すると、必ず相談に応じてくれます。このように、公的な機関を利用することも場合によっては有効です。
知っていますか?保険のこと。
好きなこの仕事を長く続けたい…。 けれど歯科業界は、職場の規模が小さく、また自分にぴったり合った医院に巡り合うまでには、転職が多いのも事実…。
そうなれば自分の社会保険などについても勉強し、一生を通じてその時々のライフスタイルに合わせながら管理をすることも、プロへの第一歩かもしれません。
| 保険の種類 | 保険者 | どんな保険? | ひと月の保険料は | |||
| 社会 保険 |
年金 | 国民年金保険 | 老齢 | 国 | 20歳以上60歳未満のすべての人が老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときに「基礎年金」を支給する公的年金制度 | 14,660円(第1号被保険者の場合) |
| 厚生年金保険 | 社会保険 事務所 |
厚生年金保険に加入している事業所の従業員が加入する年金制度(内容は国民年金+αとなっている、少し手厚い年金制度) | 標準報酬月額の15.350%。会社と労働者が半分づつ負担。 | |||
| 健康 保険 |
政府管掌健康保険 | 疾病 | 全国健康 保険協会 |
健康保険組合に加入していない医院で働いている人が加入する医療保険 | 都道府県ごとに異なる | |
| 組合管掌健康保険 | 健康保険 組合 |
健康保険組合に加入している医院で働いている人が加入する医療保険 | 組合ごとに異なる。会社と労働者が半分づつ負担。 | |||
| 国民健康保険 | 市町村及び 特別区 |
上記2つの健康保険に加入していない人が必ず加入する医療保険 | 市町村及び特別区ごとに異なる | |||
| 介護保険 | 介護 | 市町村及び 特別区 |
40歳以上65歳未満のすべての人 | 市町村及び特別区ごとに異なる | ||
| 労働 保険 |
労災保険 | 労働 災害 |
国 | 業務災害及び通勤災害にあった労働者又はその遺族に、保険給付を支給する政府管掌の保険制度。 | 事業主が全額負担 | |
| 雇用保険 | 失業 | 国 | すべての事業所で加入しなければならない強制保険(個人経営で従業員4人以下の農林水産業を除く)。 | 賃金の1.1%。そのうち労働者は0.4%負担。残りを会社が負担。 | ||
仕事をしていてもしていなくても、いつも年金にひとつ、健康保険にひとつ、加入しましょう(配偶者等の扶養になっている期間は、年金に加入していなくても、第3号被保険者と認められます)。国民健康保険や、介護保険は、市区役所で手続きができます。
健康保険については、医院によっては、歯科医師国民健康保険に加入しているところもあります。
そうでない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。国民健康保険については、医院側が支払う義務はないのですが、好意で半額を負担している医院などもあり、医院によって多少違いがあります。
労働保険は、仕事をしている間にかける保険です。仕事についたとき、雇用主に相談してください。
労働時間について
8時間以上の勤務には、残業手当が発生します。
休憩時間については、1日8時間をこえる場合には1時間、6時間をこえ8時間までは45分と定められています(6時間以内であれば休憩時間はなしでもよい)。
有給休暇について
有給休暇は、正式に働き始めてから6ヶ月たち、出勤率が8割以上であれば、法律で下記のように付与されることが決められています。申請する時期などについては、最初に医院と確認しておくとよいでしょう。
<有給休暇の付与日数>
| 勤続年数 | 6ヵ月 | 1年 6ヵ月 |
2年 6ヵ月 |
3年 6ヵ月 |
4年 6ヵ月 |
5年 6ヵ月 |
6年 6ヵ月以上 |
| 有給休暇の 付与日数 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
賃金について
最低賃金は、都道府県により設定されています。普通の時給でそれを下回っているケースはほとんどないようですが、気になる方は次を参考にしてみてください。
厚生労働省ホームページ:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
解雇について
雇用から14日以内に限って、医院は従業員をすぐに解雇してもよいことになっています。
それ以降は、医院が設定した「試用期間」内であっても、解雇する場合の通知は、30日前にしなくてはいけないきまりになっています。もし通知がなかった場合、医院は解雇する従業員に30日分の平均賃金を支払う義務が生じます(通知から15日後の解雇であれば、15日分の平均賃金)。これを解雇予告手当といいます。
退職金について
退職金については、医院側が特に設けなくてはいけないという規則は実はありません。最初に、どうなっているか確認しておくとよいでしょう。
【以上の内容について、法の改正等により、事実と異なる場合もあります。詳しくは専門家にご確認下さい。また、他コンテンツへの文章の引用・転載を禁じます。】